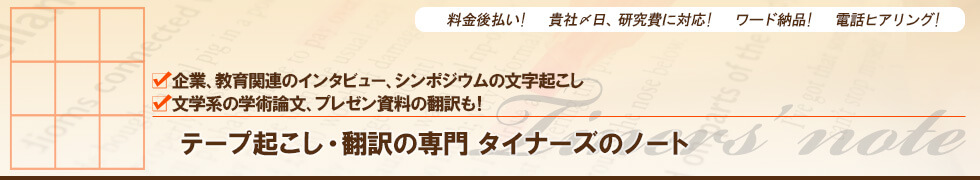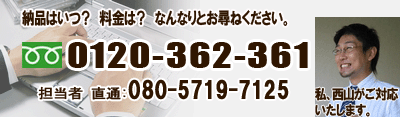2025/01/23
下記をアップしました。
説明するとこういうことになりますが、実際やってみると「思ったより難しい…」ってなりますよね。
1. コードの粒度(細かさ)に迷う
どこまで細かく切り取るべきか、逆にどこまで抽象化してまとめるかの加減が難しいです。細かくしすぎると全体像が見えなくなるし、大雑把にしすぎると意味がぼやけてしまう。まさにバランス感覚が問われます。
2. 自分の解釈が入りすぎることへの不安
発言をコードにするとき、どうしても自分なりの解釈が入りますよね。それが「勝手な読み取りになってないかな?」という不安がつきまといます。質的研究は主観を排除できないからこそ、慎重さと自信のバランスが難しい。
3. カテゴリのグルーピングがしっくりこない
似ているようで違う発言、違うようで似ている発言… どこを同じグループにまとめるべきか、本当に悩みます。「なんとなく分かるけど言語化が難しい」みたいなモヤモヤが続くことも。
4. 論文の流れとの接続が見えにくい
コードとカテゴリは作れた。でも「これをどう論文の構成に活かすの?」となったときに、意外と手が止まります。素材はあるのに、料理の仕方がわからない感じ。ここで挫折しそうになる人も多いです。
5. 「正解がない」ことそのもの
数値で測れないし、唯一の答えもない。だからこそ自由度が高い反面、「これで合ってるのかな…?」という不安が最後までつきまとう。質的研究の醍醐味でもあり、難しさでもあります。
これらの「難しさ」は、むしろ質的研究を深くしてくれるきっかけでもあるんですけどね。
でも、独りでやってるとしんどいので、他の人の視点やフィードバックってけっこう大事だったりします。
質的研究って、一見「対話的」な手法っぽく見えるけど、実際に論文に落とし込むプロセスはめちゃくちゃ孤独な知的作業なんですよね。
誰かと一緒にインタビューをしたり、議論したりするときは活発で楽しいのに、
いざ一人でコード化を始めて、「この表現どうまとめよう…」「このカテゴリって本当に意味あるのかな…」みたいに悩み出すと、ぐるぐる思考の沼にハマる感じ。
しかも、解釈って主観が入るから、「これでいいのかな?」の不安に答えてくれる正解がどこにもない。
「なんとなくいい気がするけど、でも誰かに確認したい…」っていう、あの状態。
だけどそれを聞ける相手がいないと、だんだん自分の見方に自信が持てなくなってくるんですよね。
だからこそ、誰かに話しながら考える機会があると、本当に救われる。
「こんなふうに読んだんだけど、どう思う?」って話すだけで、視点が整理されて、スッと腑に落ちることもあるし。
独りでがんばってる人に「わかるよ、それでいいんだよ」って言ってくれる誰かがいると、ぜんぜん違いますよね。
半構造化インタビュー 文字起こし+コード化・カテゴリー化はこちら
https://www.tapeokoshi.net/semi-structured/